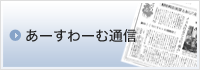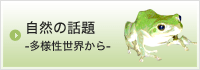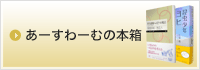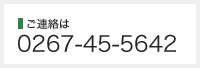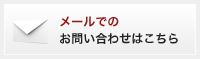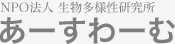トップページ > メンバー
メンバー
南 正人(代表理事)
野生動物学が専門です(学位論文はニホンジカの鳴き声の分類と機能)。宮城県の金華山島で、名前をつけた野生のシカ1000頭の一生を30年間追跡しています。軽井沢で15年間自然ガイドに従事し、麻布大学で13年間教員生活を送りました。軽井沢ではシカやカモシカの生態を研究しながら、行政とともに被害防除の仕組みづくりにかかわっています。生き物の観察を通じて自然の仕組みを理解し共感を得るような環境教育の普及やエコツーリズムに取り組んでいます。著作は「シカの顔,わかります」(東京大学出版会)、「野生動物の行動観察法」(東京大学出版会 共著)、「野生動物への2つの視点」(ちくまプリマー新書 共著)、「動物たちの気になる行動(2)」(裳華房 共著)など。
山下国広(理事)
獣医師/ドッグトレーニングインストラクター。長年,家畜診療にたずさわる傍らボランティアで犬のトレーニング指導をおこなってきましたが,2005年に独立開業。家庭犬のしつけ指導や問題行動修正のほか,ベアドッグ,里守り犬(サル・シカ等の対策犬),外来動物探索犬などの育成に関わっています。
自身のHP:http://homepage2.nifty.com/beh-vet/
福江佑子(理事)
野生動物保護学、動物生態学が専門です(特に中型の食肉類)。学生の時にはタヌキの生態研究を行いました。現在は、アライグマ、ハクビシン、アメリカミンクなど外来生物の排除対策のほか、シカが生態系に及ぼす調査などに携わっています。動物達の「死」に関わることも多く、時に迷いながら、時に自分を叱咤しながら、野生動物と人との問題に取り組んでいます。長野県希少野生動植物対策委員、長野県生物多様性策定委員、長野県環境審議会委員などを務めてきました。
(以下、五十音順)
葦田恵美子
こどものころ、よく遊びに連れて行ってもらった阿蘇で出遭ったタヌキやキツネに魅せられ、現在、野生動物にかかわる仕事に携わっています。これまで、外来種のアライグマ・アメリカミンクの防除対策や、ニホンザルによる被害対策など、野生動物とヒトとの軋轢の問題に関わってきました。好きで足を踏み入れたこの仕事ですが、「素晴らしい自然」というだけでは解決できない数多くの問題に苦悩する毎日です。故郷である熊本で、野生動物とヒトとの仲介人になり、自然と上手くつきあっていける地域をつくることが将来の目標です。
石塚 徹
専門は動物社会学・行動生態学で、「クロツグミのさえずりに表れる複婚戦略」の進化的な意義を博士論文にまとめました。無名な生きものを表舞台に上げること、一つでも多くの種の生息環境を歩き、体で理解することをめざします。「子どもの好きなことをのばしてやりたい」という教育方針の家庭向けに、探究学習のプログラムを作ります。著書に「歌う鳥のキモチ」(山と渓谷社)、「昆虫少年ヨヒ」(郷土出版社)、「ゆかいな聞き耳ずきん」(福音館書店「たくさんのふしぎ」傑作集)、「野鳥界〈識別編〉〈生態編〉」(信濃毎日新聞社)、「鳥のおもしろ私生活」(主婦と生活社)など。万座しぜん情報館顧問(初代館長)。
大西 信正
宮城県金華山島のニホンジカの研究に1989年から携わっています。同時に、軽井沢で森のガイドを15年近く行ってきましたが、現在は(株)生態計画研究所に所属し、山梨県早川町の南アルプス生態邑に赴任しています。そこでは、野生動物や山里文化などのインタープリテーションを行っています。 子供の頃から生き物が好きで、生き物の心が知りたくて、研究とガイドの業界で活動しています。モットーは「思いやりの心と科学の目」です。
佐藤美幸
一年のうち半分を尾瀬で、もう半分を長野県で過ごしています。尾瀬では、半年間住み込みで仕事をしています。毎年毎日、同じようで違う尾瀬の姿に目が離せない日々です。長野県では、哺乳類の死体から研究用のサンプルを採取したり、分析する仕事をしています。作業の中で見えてくる動物たちの姿は十人十色です。色々な面から自然を見ることで、生き物の生活や生き物同士の関わりを知りたいと思っています。
樋口 洋
専門学校生の時から宮城県金華山島や青森県下北半島に通い、ニホンジカやニホンザルを観察する日々を過ごし、個体を見続ける面白さを知りました。その後は野生生物保護管理や国立公園内の施設管理、農業などの仕事に携わり、人と生き物たちの係わり合いに関心を持ち、まずは自分自身が自然とどう向き合うか考える日々です。
樋口 尚子
動物行動学が専門で、宮城県金華山でシカを個体識別し、繁殖や社会行動の研究を20年以上続けています。シカは個体群として扱われることの多い動物ですが、個体ごとに個性があり、生存戦略も異なります。それを知ることが「シカを科学する」ことだと思います。最近は金華山にとどまらず、シカとシカ糞を求めて、全国行脚、調査の旅をしています。
(このほかに数名のメンバーがいます)